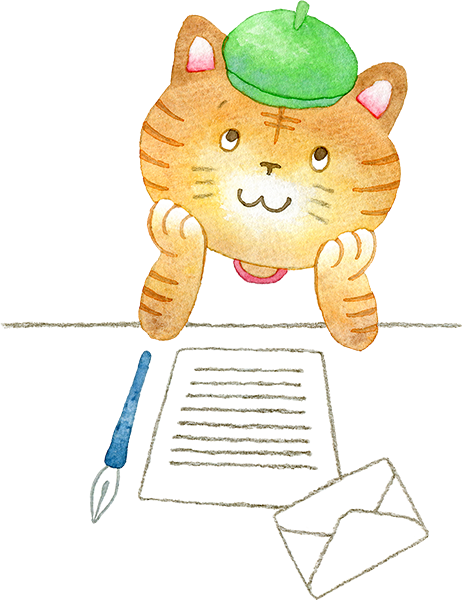発達障害について(その1)総論

今回から数回にわたり、発達障害についてお話ししたいと思います。発達障害は生まれつきの脳の性質であって、いわゆる「子どものこころの問題」とはちょっと違うかもしれません。しかし、人が生まれつき持っている性質というのは、その人の考え方や社会との関わりに大きな影響を及ぼします。そして、考え方や社会との関わりのパターンによって、人はストレスを抱えやすくも抱えにくくもなるのです。
どんな病気でも、その発症には「素因」と「環境」が関わっています。素因とは子どもがもともと持っている性質、環境は子どもを取り巻く周囲の状況です(子どもの生活に大きく関わるものとしては、家庭環境と学校環境があります)が、発達障害は子どもの素因として重要なもののひとつです。よって、発達障害を知ることは、子どものこころの問題を考えるうえでとても大切なのです。
子どもは生まれてから、日々成長・発達していきます。「この時期にはこのくらいのことができるようになる」という成長・発達のパターンは多くの子どもである程度一定なので、乳幼児健診では、子どもがその時期の発達の指標をクリアしているかどうかを確認することで、子どもの発達が正常なのかどうかを判定します。そして、発達の過程が明らかに通常よりもゆっくりだったり、バランスが悪かったりする(発達するところとしないところがまだらにある)ものを発達障害といいます。
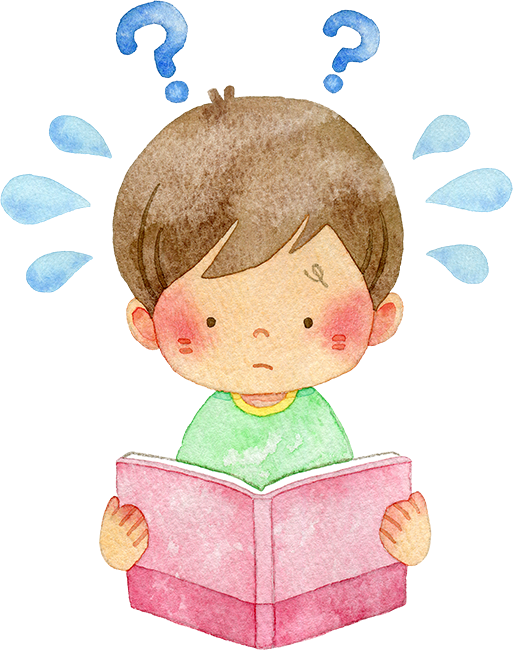
知的障害、注意欠如・多動症(ADHD)、自閉スペクトラム症(ASD)、学習障害(LD)、発達性協調運動障害など、発達障害にはいろいろな診断名がありますが、それは、子どもの発達の問題点の違いによっていろんなパターンがあると考えてもらえればよいでしょう。ただし、それらは診断ごとに明確に色分けできるものではありません。子どもによって発達のパターンはさまざまですから、実際にはいろんな色が混じり合っている(いろんな診断が重なり合っている)のだといえます。
発達障害は20年ほど前から注目されるようになり、今ではおそらく聞いたことがない人はいないだろうというくらい知られるようになりました。しかし、発達障害ほど正確に理解されていないものはないかもしれません。それは、ひとつには「衝撃的な事件を起こした子どもが発達障害だった」という報道が相次いだことが関係しているように思います。それによって発達障害は「特別」でかつ「危険」なものと捉えられるようになってしまいました。しかし本来、発達障害はそんなに特別なものではありません。
発達障害に対するいちばんの誤解は「障害」という名称にもあります。日本語で「障害」というと「固定的で、この先ずっと変わらない問題」と感じられてしまいますが、決して発達障害とはそのようなものではないのです。
発達障害は子どもにとっては「現時点における」発達の滞りあるいは偏りであって、それは決して取り返しがつかないものではありません。もちろん、程度がひどい場合には将来的にも残ってしまいますが、一時的な滞りとして将来は改善する可能性があるものも多いのです。つまり、発達障害は固定的な「障害」とは明らかに異なります。

それではどうして「障害」といわれるようになったのでしょうか。それは、英語の診断基準を日本語にする際にdisorder(不調、混乱、正常から外れているという意味)を「障害」と訳してしまったからです。近年、それを見直そうという動きが広がり、「障害」ではなく「症」と訳すように変わってきています。そのため「発達障害」も「神経発達症」と呼ばれるようになりました。また、発達障害の特性は誰もが持つものであり、違うのはその濃淡だという意味で、「スペクトラム」という表現が用いられるようになっています。
医学的には「誰にでもある特性だけど、その特性がかなり強く、日常生活や社会適応に問題を生じているとき」に神経発達症(発達障害)と診断されます。しかし、年齢を重ねて発達が進んでいくにつれて、問題となる特性が薄まって、社会適応上の問題も消失していく場合が多々あります。特性はあるが「診断域ではなくなった」ということです。そのときは、子どもに見られた発達の滞りは一時的なものであり、成長するにつれてキャッチアップしたということになります。もちろん、特性はまったく消えてなくなったわけではなく、根っこの部分では残っているのですが、適応上問題となる程度ではなくなったということです。
ところが、年齢が進んでも特性の強さがどうしても診断域以下にならない場合もあり、そのときには、成人以降もずっと持ち越すと考えなければなりません。そのような特性は、今後も続いていく「障害」と考えた方がよいでしょう。いわゆる「大人の発達障害」とはそういうものです。大人になって発現したものではなく、子どもの頃からあった問題が大人まで持ち越されたというわけです。
それでは、来月以降は、いろいろな発達障害について1つずつ詳しくお話ししていきたいと思います。
著者
| 著者 | 小柳憲司(コヤナギ ケンシ) |
|---|---|
| 所属・役職 | 長崎県立こども医療福祉センター副所長兼医療局長 |
| 長崎大学医学部、長崎大学教育学部、佐賀大学医学部、長崎医療技術専門学校非常勤講師 | |
| 専門領域 | 小児科学、心身医学 |
| 主な著書 | 身体・行動・こころから考える 子どもの診かた・関わりかた(新興医学出版社) 学校に行けない子どもたちのための対応ハンドブック(新興医学出版社) |
この記事の感想をお聞かせください
この記事についてのご意見やご相談等をお送りください。