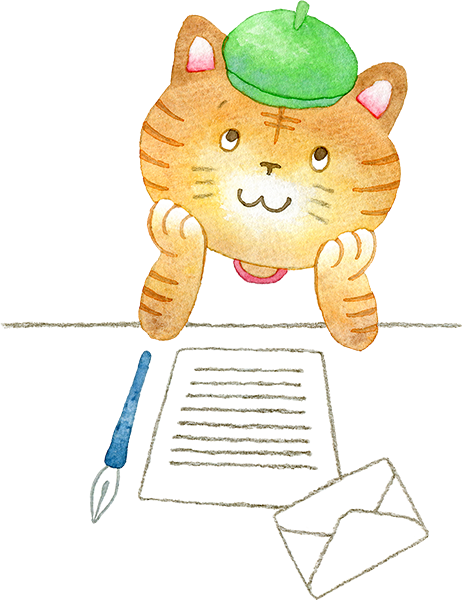排泄に関わる問題(その2:夜尿症)

3歳頃までの子どもが夜間におしっこをもらしてしまうのは生理的なものです。当たり前のことだからこそ、小さな子どもはみんなオムツをして寝ています。年齢が上がるとだんだん夜におしっこをもらすことは減っていき、夜のオムツも卒業していきます。
4~5歳の頃はまだときどき失敗することがあり、そんなときには「おねしょしちゃったね」といわれますが、小学校に上がるくらいまで続くと「ちょっと長引いてない?」ということになり、その頃になってもおねしょが続くものを「夜尿症」といいます。
夜間の排尿コントロールに関わるのは、次の3つです。
- 夜間に作られるおしっこの量が十分少なくなる
- 夜間の膀胱容量が十分大きくなる
- 尿意(おしっこをしたいという感覚)で目が覚めるようになる
赤ちゃんの頃は、昼夜関係なく薄いおしっこが一定量ずつ作られますが、年齢が上がると、昼間には多く、夜になると少なくなる、というリズムができてきます。「朝のおしっこは色が濃くて臭いも強いな」と思ったことはありませんか?夜間はおしっこの水分が身体に再吸収されておしっこが濃くなる分、量は少なくなるのです。また、夜間睡眠に入ると緊張がほぐれるために膀胱の筋肉が伸び、容量が増えます。おしっこの量が減り、溜められる量が増えるために、朝まで膀胱がいっぱいにならずにすむようになるのです。
もし、膀胱がいっぱいになったとしても、トイレットトレーニングが完了していれば、昼間は「おしっこをしたい」という感覚が脳に生じるので、トイレに行って排尿することができます(トイレットトレーニング完了前は、膀胱がいっぱいになったら尿意が生じる前に自律的に膀胱が収縮して排尿してしまいます)。睡眠中も膀胱におしっこが溜まれば尿意が生じ、その尿意で目が覚めてトイレに行くことができればおねしょはしません。なので、尿意で目が覚めるかどうかも夜尿症には大きく関わります。

このような排尿コントロールは成長とともに徐々に確立していくものですから、夜尿症はその発達が遅いというだけで、そもそも「こころの問題」というわけではありません。ただし、夜尿症があることで「恥ずかしい」と強く感じたり、いろんな活動(とくに宿泊を伴う行事)に参加するのをしり込みしたりするようになれば、それは、子どものこころの発達に悪影響を及ぼします。
また、二次性夜尿といわれる、いったん夜尿症が治った後にまた出現してきたものについては、心理社会的なストレスとの関係が深いといわれています。もともと夜尿症があり、治ったと思ったのにまた最近失敗するようになった、というときには、何かストレス状況があるのではないかと考えることが必要です。
夜尿症の治療の中心は生活指導で、次のような指導を行います。
- 水分は午前中に多く摂り、夕方以降は少なくする。それによって、昼間のおしっこの量を多く、夜間に少なくするというリズムを作る。
- 夕食はできるだけ早い時間に、できるだけ薄味のものとし、汁物などの水分はできるだけ少なくする。摂取した水分は3時間でその80%がおしっことなり排泄されるといわれているため、夕食以降の水分摂取はできるだけ控え、最後に水分を摂って3時間以上してから、しっかり排尿して寝るようにする。
夕方からスポーツクラブなどに参加する子どももいて、これらをきちんと守るのは難しいかもしれません。そのときには、できる範囲でやっていけばよいでしょう。
生活指導に続いてよく行われるのがアラーム療法です。これは、パンツがぬれたらアラームが鳴ったり、バイブレーションしたりする機器を使う方法です。機器自体はネットでも買えますが、使い方については医師に相談した方がよいでしょう。
その次が薬物療法になります。おしっこの生成量を減らす薬や、膀胱容量を増やす薬を使います。生活指導は小学校低学年から行いますが、薬物療法を始めるのは高学年以降が多いようです。このような治療によって、小学校入学の頃100人あたり10人くらいいる夜尿症の子は、年間1~2人くらいずつ減っていき、中学入学の頃には1人くらいになるといわれています。

夜尿症は排尿コントロールの発達が遅いのだという話をしましたが、発達が遅いという点では、身体的発達が遅い子どもや、能力的な発達が遅い、あるいは発達にばらつきがある子ども、すなわち神経発達症(発達障害)の子どもに比較的多くみられます。そして、治癒が遅れるのも神経発達症の子どもに多い印象があります。
神経発達症の子どもたちは自分に自信がもてないことが多く、夜尿症があることもその一因となります。どんどん治療したら早く治るというものではありませんが、「しっかり治療に取り組んでいけば、いつか必ず治るよ」と伝え、治療意欲を高めていくことが大切です。
夜尿症があると宿泊学習や修学旅行、部活の合宿などに参加するのがおっくうになりがちで、それがさらなる自己肯定感の低下を招きます。「ちゃんと先生に相談して夜中に起こしてもらうようにするから大丈夫」「あなただけじゃない、おねしょする子はたくさんいるんだよ。誰も自分からは言わないけどね...」などと話し、親の方が勇気と自信をもって送り出してあげるようにしましょう。
著者
| 著者 | 小柳憲司(コヤナギ ケンシ) |
|---|---|
| 所属・役職 | 長崎県立こども医療福祉センター副所長兼医療局長 |
| 長崎大学医学部、長崎大学教育学部、佐賀大学医学部、長崎医療技術専門学校非常勤講師 | |
| 専門領域 | 小児科学、心身医学 |
| 主な著書 | 身体・行動・こころから考える 子どもの診かた・関わりかた(新興医学出版社) 学校に行けない子どもたちのための対応ハンドブック(新興医学出版社) |
この記事の感想をお聞かせください
この記事についてのご意見やご相談等をお送りください。