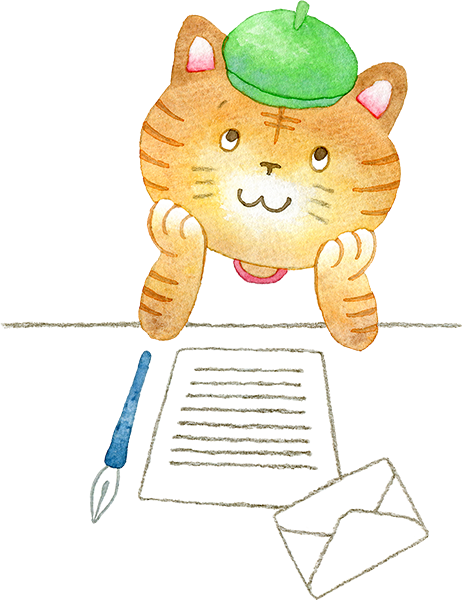排泄に関わる問題(その1:心因性頻尿)

今回から数回にわたり、排泄に関わる問題についてお話ししていきましょう。
排泄とその処理が自分でできるようになることは、人が尊厳をもって社会生活を送れるようになるために非常に大切です。だからこそ、トイレットトレーニングは子どもが成長していくうえでの一大イベントになるのでしょう。
乳児期には、排泄は自律的に行われます。すなわち、おしっこが膀胱にいっぱいになったら自動的に膀胱の収縮が起こり排尿する、直腸部にうんちが溜まると反射が起こり排便するといった具合です。しかし、年齢が上がると、おしっこが膀胱に溜まる、うんちが直腸に溜まるという感覚が少しずつわかるようになります。そして、もよおしている様子を周囲の大人が気づいてトイレに連れていき排泄を促す、うまくできたら盛大に褒める、という作業の繰り返しから、少しずつ意思の力で排泄のコントロールができるようになるのです。その過程がトイレットトレーニングです。
トイレットトレーニングの途中や、排泄のコントロールが確立してしばらくは、まだその状態は安定しているとはいえません。そのため、失敗することもありますし、失敗しないように子どもが尿意や便意に過剰に注目した結果、トラブルが生じる場合があります。心因性頻尿とはそのような状態です。具体的には、幼稚園児くらいの子どもが「急に頻繁におしっこに行くようになった」というもので、家族から「この子、最近5分ごとにおしっこに行くんです。行っても出ないときもあるのに...」などと相談されます。

おしっこが頻回にあるのを頻尿と言いますが、医学的には頻尿を診たら、膀胱炎などの炎症がないか、頻尿だけではなく実際に尿量が増えていないか(尿量が増えるのは、尿崩症や糖尿病でみられます)を鑑別します。それは、検尿したり飲水の量をチェックしたりすればわかりますから、一定の検査をしたうえで異常がなければ、おしっこのことが過剰に気になっている状態だということになります。
身体的には大きな問題はありませんから、「トイレットトレーニングが終わったばかりの頃は、おしっこのことが過度に気になって何度もトイレに行くようになる時期があるんですよ、だから気にせず様子を見ておいてください。1~2週間で治まります」と説明します。心配している家族を安心させることが大切です。
ただし、心因性頻尿には、より大きな問題となるものがあります。それは、学校に入ってから起こるものです。学校生活は時間で区切られており、トイレにも自由に行けません。授業中にもよおせば、先生に「トイレに行きたいので行かせてほしい」と表明しないといけないわけです。いまどき「がまんしなさい」という先生はいないでしょうが、引っ込み思案な子はなかなかそれが言えませんし、クラスメイトから笑われそうで言えない子もいるでしょう。その結果、教室内で漏らしてしまうと、それからおしっこのことがすごく気になって教室に入れなくなるということが起こります。
ひどくなると外に出ること自体が不安になり、学校にも行けなくなる場合があります。外出しようとするとトイレのことが気になって、ちょこちょこコンビニのトイレなどに寄らなくてはいけなくなるので外出が難しくなるし、トイレがないバスなどにはとても乗れなくなってしまうのです。

このような状態になると、改善にはかなりの時間がかかります。不安を緩和するために、膀胱の活動を抑制して尿意を感じにくくする薬や、不安を緩和する薬を使いながら、少しずつ外出を促します。外出先ではどこにトイレがあるかをあらかじめ把握しておけば、不安の緩和につながります。
学校に行ける場合には、教室に入ることを無理強いせず別室登校にしたり、教室の席を後ろのドアのそばにして、いつでもトイレに行けるように配慮したりします。学習についてはオンラインなどで保証し、時間をかけて少しずつ改善を待つことが大切です。デリケートなことだからこそすごく気になるし、思春期の子どもであればなおさらです。治療においても十分な配慮が必要であるといえるでしょう。
著者
| 著者 | 小柳憲司(コヤナギ ケンシ) |
|---|---|
| 所属・役職 | 長崎県立こども医療福祉センター副所長兼医療局長 |
| 長崎大学医学部、長崎大学教育学部、佐賀大学医学部、長崎医療技術専門学校非常勤講師 | |
| 専門領域 | 小児科学、心身医学 |
| 主な著書 | 身体・行動・こころから考える 子どもの診かた・関わりかた(新興医学出版社) 学校に行けない子どもたちのための対応ハンドブック(新興医学出版社) |
この記事の感想をお聞かせください
この記事についてのご意見やご相談等をお送りください。